 HOME HOME  大学TOP 大学TOP  文学部 文学部  お問い合わせ お問い合わせ  |
第41号
文学部日本文学科主催
国際学術シンポジウム
『「源氏物語と和歌世界」について』
二〇〇六年一月一四日(土)、前年に開催された国際学術シンポジウム「文字とことば―古代東アジアの文化交流―」に引き続き、「源氏物語と和歌世界」が青山キャンパスにおいて開催されました。学外から、東京大学大学院教授藤原克己先生、コロンビア大学東アジア言語・文化学部教授ハルオ・シラネ先生をお招きし、本学科の土方洋一先生とともに基調報告をなさいました。司会をお務めになったのは高田祐彦先生です。
『源氏物語』にとっての和歌、また和歌にとっての『源氏物語』とは何であるのかという問いかけの上に立ち、『源氏物語』と和歌世界との関係を日本文学史ひいては日本文化全体の中でどのように考えるべきなのか、といった問題意識のもとに今回のテーマが立てられました。
藤原克己先生は「「袖ふれし人」は薫か匂宮か―手習巻の浮舟の歌をめぐって―」、ハルオ・シラネ先生は「夕顔、詩歌、絵画―創作的読みの力」、土方洋一先生は「物語作中歌の位相」というタイトルでそれぞれご報告されました。三名の先生方の報告と、あらかじめ来聴の方にお配りしていた質問用紙に基づいての活発な討論が行われ、更なる研究の展望が開けたように思います。『源氏物語』と和歌というテーマが孕んだ様々な問題を興味深く捉え直すきっかけができ、非常に有意義なシンポジウムでした。
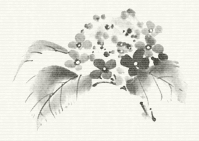
当日は雨という悪天候であったにも関わらず、多くの方が会場に足をお運び下さり、テーマや古典文学に関する関心の高さをうかがい知ることができました。分野における専門の方々だけでなく、一般の方々も大勢興味をお持ちくださったらしく、皆さん熱心にメモを取りながら聴講してくださいました。こうした貴重な催しが青山学院大学において行われるということの素晴らしさを改めて実感するとともに、今後も同様の企画を継続していってくださるよう、日本文学科学生の一人として期待したいと思います。
国際学術シンポジウム
『「源氏物語と和歌世界」について』
M2 長尾文子
二〇〇六年一月一四日(土)、前年に開催された国際学術シンポジウム「文字とことば―古代東アジアの文化交流―」に引き続き、「源氏物語と和歌世界」が青山キャンパスにおいて開催されました。学外から、東京大学大学院教授藤原克己先生、コロンビア大学東アジア言語・文化学部教授ハルオ・シラネ先生をお招きし、本学科の土方洋一先生とともに基調報告をなさいました。司会をお務めになったのは高田祐彦先生です。
『源氏物語』にとっての和歌、また和歌にとっての『源氏物語』とは何であるのかという問いかけの上に立ち、『源氏物語』と和歌世界との関係を日本文学史ひいては日本文化全体の中でどのように考えるべきなのか、といった問題意識のもとに今回のテーマが立てられました。
藤原克己先生は「「袖ふれし人」は薫か匂宮か―手習巻の浮舟の歌をめぐって―」、ハルオ・シラネ先生は「夕顔、詩歌、絵画―創作的読みの力」、土方洋一先生は「物語作中歌の位相」というタイトルでそれぞれご報告されました。三名の先生方の報告と、あらかじめ来聴の方にお配りしていた質問用紙に基づいての活発な討論が行われ、更なる研究の展望が開けたように思います。『源氏物語』と和歌というテーマが孕んだ様々な問題を興味深く捉え直すきっかけができ、非常に有意義なシンポジウムでした。
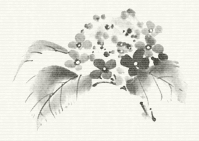
当日は雨という悪天候であったにも関わらず、多くの方が会場に足をお運び下さり、テーマや古典文学に関する関心の高さをうかがい知ることができました。分野における専門の方々だけでなく、一般の方々も大勢興味をお持ちくださったらしく、皆さん熱心にメモを取りながら聴講してくださいました。こうした貴重な催しが青山学院大学において行われるということの素晴らしさを改めて実感するとともに、今後も同様の企画を継続していってくださるよう、日本文学科学生の一人として期待したいと思います。
海を渡る文学
―日本と東アジアの物語・詩・絵画・芸能―
博士後期課程院生 山本啓介
二〇〇六年九月二日(土)、まだ夏の熱気の残る午後の青山キャンパスにて、本学日本文学科主催の国際シンポジウムが開催された。本年度のテーマは中世の日本と東アジアとの文学・絵画・芸能などにおける文化交流についてであった。
まず、佐伯真一氏「日本中世文学研究の内外」は、『平家物語』中の説話に見られる、中国や韓国の説話との共通点を紹介され、中世文学において、アジア圏の広がりと向きあうことの重要性を述べて、シンポジウムの見通しを述べられた。
楊暁捷氏「詩の物語・絵の物語」は、北方の異民族に嫁した悲劇の女性、蔡文姫を描いた絵巻『胡茄十八拍図』の絵と詩を読み解かれ、その絵画と詩(物語)の内容が完全に一致せず、絵画は絵画として独立した存在となっている点を指摘され、地の文と絵との融和性の高い日本の絵巻との性格の相違などについて述べられた。
邊恩田氏「〈四方四季〉と日本文学」は、日本の古典作品中にも登場する、部屋の四方に描かれる四季を描く〈四方四季〉について、特にパンソリ『春香伝』と朝鮮時代の古典『金鰲新話』中における四方絵の東西南北に配される画中の人物の変容などの展開を整理された。
村井章介氏「肖像画・賛からみた禅の日中交流」は、中世の画賛を数多く紹介され、日本において描かれた高僧の肖像画に付すための賛を、唐の僧に要請していた例などもあることを指摘、「海を渡る文学」として画賛を見る視点を示された。
その後の討論も活発に行われ、気がつけば刻限も過ぎ、夕風も涼しい頃となっていた。閉会の後に、日本とは何か、国際化とは何かをあらためて考えさせられた。「日本論」やら「国際」という便利な用語は、時として単純な絶対化や、安易な比較論となりやすい。今回のシンポジウムは、中世東アジアの文化は同じ一つの根から生じたものもあり、また相互に影響し合いながら、それぞれに独自性が育ったものである、という様相の一面を示した。これは一つの達成であったと思われる。文学作品を捉える上で、往時の日本が属していた東アジアの文化圏との関わりの中から位置づけてゆくことの必要性を学ばせていただいた。
―日本と東アジアの物語・詩・絵画・芸能―
博士後期課程院生 山本啓介
二〇〇六年九月二日(土)、まだ夏の熱気の残る午後の青山キャンパスにて、本学日本文学科主催の国際シンポジウムが開催された。本年度のテーマは中世の日本と東アジアとの文学・絵画・芸能などにおける文化交流についてであった。
まず、佐伯真一氏「日本中世文学研究の内外」は、『平家物語』中の説話に見られる、中国や韓国の説話との共通点を紹介され、中世文学において、アジア圏の広がりと向きあうことの重要性を述べて、シンポジウムの見通しを述べられた。
楊暁捷氏「詩の物語・絵の物語」は、北方の異民族に嫁した悲劇の女性、蔡文姫を描いた絵巻『胡茄十八拍図』の絵と詩を読み解かれ、その絵画と詩(物語)の内容が完全に一致せず、絵画は絵画として独立した存在となっている点を指摘され、地の文と絵との融和性の高い日本の絵巻との性格の相違などについて述べられた。
邊恩田氏「〈四方四季〉と日本文学」は、日本の古典作品中にも登場する、部屋の四方に描かれる四季を描く〈四方四季〉について、特にパンソリ『春香伝』と朝鮮時代の古典『金鰲新話』中における四方絵の東西南北に配される画中の人物の変容などの展開を整理された。
村井章介氏「肖像画・賛からみた禅の日中交流」は、中世の画賛を数多く紹介され、日本において描かれた高僧の肖像画に付すための賛を、唐の僧に要請していた例などもあることを指摘、「海を渡る文学」として画賛を見る視点を示された。
その後の討論も活発に行われ、気がつけば刻限も過ぎ、夕風も涼しい頃となっていた。閉会の後に、日本とは何か、国際化とは何かをあらためて考えさせられた。「日本論」やら「国際」という便利な用語は、時として単純な絶対化や、安易な比較論となりやすい。今回のシンポジウムは、中世東アジアの文化は同じ一つの根から生じたものもあり、また相互に影響し合いながら、それぞれに独自性が育ったものである、という様相の一面を示した。これは一つの達成であったと思われる。文学作品を捉える上で、往時の日本が属していた東アジアの文化圏との関わりの中から位置づけてゆくことの必要性を学ばせていただいた。
Copyright© 2005 Japanese Literature, College of Literature, Aoyama Gakuin University. All Rights Reserved.


