 HOME HOME  大学TOP 大学TOP  文学部 文学部  お問い合わせ お問い合わせ  |
第40号
文学部日本文学科主催
国際学術シンポジウム
「文字とことば―古代東アジアの文化交流―」
3月12日(土)午後1時から、青山キャンパスにおいて標記のシンポジウムが開催されました。古代中国を中心に形成された東アジア漢字文化圏にあって、漢字を母語としない周辺諸民族が漢字とどのように向き合い、どのように馴致していったのか、その諸相と展開を学際的に展望するというのが、このシンポジウムの目的です。そのため、学外から壇國大学名誉教授南豊鉉先生(韓国語学)・広島大学名誉教授小林芳規先生(日本語学)・東京大学大学院教授佐藤信先生(歴史学)の3名と本学科教員3名―安田尚道先生(日本語学)・高田祐彦先生(中古文学)・小川靖彦先生(上代文学)―に基調報告をお願いしました。
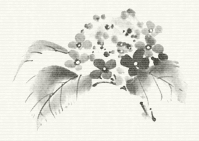 各基調報告のタイトルは、「古代東アジアの国際環境(佐藤信氏)」「文字の交流―片仮名の起源―(小林芳規氏)」「韓日両国の古代資料における文末助辞『之』について(南豊鉉氏)」「古代日本の漢字文の源流(安田尚道氏)」「万葉集の文字法(小川靖彦氏)」「かな文学の創出(高田祐彦氏)」の如くです。
各基調報告のタイトルは、「古代東アジアの国際環境(佐藤信氏)」「文字の交流―片仮名の起源―(小林芳規氏)」「韓日両国の古代資料における文末助辞『之』について(南豊鉉氏)」「古代日本の漢字文の源流(安田尚道氏)」「万葉集の文字法(小川靖彦氏)」「かな文学の創出(高田祐彦氏)」の如くです。
来日直前の3月9日朝、南氏が心筋梗塞の発作にみまわれ、来日できなくなるという予期せぬ事態が出来ましたが(幸い南氏からは3月2日付で報告原稿を頂戴していたので、当日は司会による要旨の紹介と原稿のコピーを配布して対応しました)、各報告はそれぞれ挑発に満ちた最先端の内容で、所期の目的は十分に果たせたと自負しています。
シンポジウム会場となった1173教室には予想をはるかに超える来場者があり、一時は立ち見の出るほどの盛況で、大幅な時間超過にもかかわらず最後の討論が終了するまで熱心にノートを取りながら耳を傾けていらっしゃいました。青山学院大学に対する世間の期待・関心の高さを知るとともに、責任の重さをも改めて実感しました。
国際学術シンポジウム
「文字とことば―古代東アジアの文化交流―」
日本文学科教授 矢嶋 泉
3月12日(土)午後1時から、青山キャンパスにおいて標記のシンポジウムが開催されました。古代中国を中心に形成された東アジア漢字文化圏にあって、漢字を母語としない周辺諸民族が漢字とどのように向き合い、どのように馴致していったのか、その諸相と展開を学際的に展望するというのが、このシンポジウムの目的です。そのため、学外から壇國大学名誉教授南豊鉉先生(韓国語学)・広島大学名誉教授小林芳規先生(日本語学)・東京大学大学院教授佐藤信先生(歴史学)の3名と本学科教員3名―安田尚道先生(日本語学)・高田祐彦先生(中古文学)・小川靖彦先生(上代文学)―に基調報告をお願いしました。
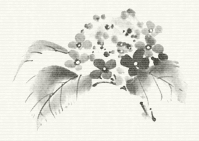 各基調報告のタイトルは、「古代東アジアの国際環境(佐藤信氏)」「文字の交流―片仮名の起源―(小林芳規氏)」「韓日両国の古代資料における文末助辞『之』について(南豊鉉氏)」「古代日本の漢字文の源流(安田尚道氏)」「万葉集の文字法(小川靖彦氏)」「かな文学の創出(高田祐彦氏)」の如くです。
各基調報告のタイトルは、「古代東アジアの国際環境(佐藤信氏)」「文字の交流―片仮名の起源―(小林芳規氏)」「韓日両国の古代資料における文末助辞『之』について(南豊鉉氏)」「古代日本の漢字文の源流(安田尚道氏)」「万葉集の文字法(小川靖彦氏)」「かな文学の創出(高田祐彦氏)」の如くです。来日直前の3月9日朝、南氏が心筋梗塞の発作にみまわれ、来日できなくなるという予期せぬ事態が出来ましたが(幸い南氏からは3月2日付で報告原稿を頂戴していたので、当日は司会による要旨の紹介と原稿のコピーを配布して対応しました)、各報告はそれぞれ挑発に満ちた最先端の内容で、所期の目的は十分に果たせたと自負しています。
シンポジウム会場となった1173教室には予想をはるかに超える来場者があり、一時は立ち見の出るほどの盛況で、大幅な時間超過にもかかわらず最後の討論が終了するまで熱心にノートを取りながら耳を傾けていらっしゃいました。青山学院大学に対する世間の期待・関心の高さを知るとともに、責任の重さをも改めて実感しました。
廣木一人著
『連歌史試論』文部科学大臣賞受賞について
博士後期課程 山本啓介
このたび、日本文学科廣木一人教授が著書『連歌史試論』(新典社、二〇〇四年)で「芭蕉祭」平成十七年度文部科学大臣賞を受賞された。
「芭蕉祭」は松尾芭蕉の命日である十月十二日に、芭蕉翁顕彰会(伊賀市)の主催で例年開催されている。同賞は、昭和二十九年の創設で、優れた連歌・俳文学の研究に贈られる賞である。
『連歌史試論』は廣木先生がこれまで取り組んでこられた連歌史に関する研究の成果を、単著としてまとめられたものである。連歌史の研究は主に昭和四十年代に金子金治郎氏や伊地知鉄男氏らの研究によって大きく進展したのであるが、それらの先学の成果が偉大であったためもあり、現在は活発に研究が前進している分野とは言えないものであった。そうした中、廣木先生は近年整備の進んでいる歴史資料や、データベースなども活用しつつ、精微な読みのもとに、膨大な資料の検証を堅実に積み重ねられた。そして、先学の時点では判明しきれなかった連歌史上の諸問題―連歌の発生、長連歌成立初期に連歌を担った者達、連歌が実際に行われた場―などに関して新見を提示された。
同賞は「連歌史全般に視点を置き、従来の連歌研究の疑問点を明らかにし、今後の連歌研究に貢献をもたらすもの」との評価を受けての受賞であった。
廣木先生はとにかくいつも歩くのがお速い。研修旅行などの際には、我々学生は振り切られないように大あわてで後をついて行くのが常である。「そんなに急いでどうするんですか」と、かつてたずねたことがある。「僕のような凡人は人の倍速く歩いて、どんどんものごとを進めて、そして人の倍は長生きするんだ。それで、やっとあれやこれやの天才的な偉い先生のような仕事ができるんだ」とのお答えが返ってきた。その自称「凡人」の先生がこのたび随分と大きな賞を受賞された。「マイペース」な先生のことなので、今後も同じく倍速で歩き、末永く御健筆で研究を進めて行かれることであろう。心よりお慶び申し上げたい。
『連歌史試論』文部科学大臣賞受賞について
博士後期課程 山本啓介
このたび、日本文学科廣木一人教授が著書『連歌史試論』(新典社、二〇〇四年)で「芭蕉祭」平成十七年度文部科学大臣賞を受賞された。
「芭蕉祭」は松尾芭蕉の命日である十月十二日に、芭蕉翁顕彰会(伊賀市)の主催で例年開催されている。同賞は、昭和二十九年の創設で、優れた連歌・俳文学の研究に贈られる賞である。
『連歌史試論』は廣木先生がこれまで取り組んでこられた連歌史に関する研究の成果を、単著としてまとめられたものである。連歌史の研究は主に昭和四十年代に金子金治郎氏や伊地知鉄男氏らの研究によって大きく進展したのであるが、それらの先学の成果が偉大であったためもあり、現在は活発に研究が前進している分野とは言えないものであった。そうした中、廣木先生は近年整備の進んでいる歴史資料や、データベースなども活用しつつ、精微な読みのもとに、膨大な資料の検証を堅実に積み重ねられた。そして、先学の時点では判明しきれなかった連歌史上の諸問題―連歌の発生、長連歌成立初期に連歌を担った者達、連歌が実際に行われた場―などに関して新見を提示された。
同賞は「連歌史全般に視点を置き、従来の連歌研究の疑問点を明らかにし、今後の連歌研究に貢献をもたらすもの」との評価を受けての受賞であった。
廣木先生はとにかくいつも歩くのがお速い。研修旅行などの際には、我々学生は振り切られないように大あわてで後をついて行くのが常である。「そんなに急いでどうするんですか」と、かつてたずねたことがある。「僕のような凡人は人の倍速く歩いて、どんどんものごとを進めて、そして人の倍は長生きするんだ。それで、やっとあれやこれやの天才的な偉い先生のような仕事ができるんだ」とのお答えが返ってきた。その自称「凡人」の先生がこのたび随分と大きな賞を受賞された。「マイペース」な先生のことなので、今後も同じく倍速で歩き、末永く御健筆で研究を進めて行かれることであろう。心よりお慶び申し上げたい。
佐伯眞一著
『戦場の精神史―武士道という幻影―』
第三回〈角川財団学芸賞〉受賞について
角川財団学芸賞は、日本の文芸・文化を扱った一般書を対象とした賞で、専門書を対象とする角川源義賞の姉妹賞として創設され、平成一五年から授与されています。対象となるのは、1、高レベルの研究水準にありながら、一般読書人にも読まれうる研究著作、2、卓抜な研究蓄積から生まれた、啓蒙的ないし評論的な著作、3、専門研究研究書からの敷衍応用として、一般性のあるテーマで独創的に構築された著作―評伝・都市や物事の個別史など、となっています。選考委員は黒田日出男堀切美山内昌之山折哲雄の諸氏です。
『戦場の精神史』は、日本の武士がだまし討ちなどせず、一騎打ちで正々堂々と戦ったというような見方は正しいのかどうかを疑い、戦場から生まれた倫理観の実像に迫ろうとした本です。実際には、合戦が繰り返された時代に育てられた倫理観は、勝つことを何よりも重視し、そのためには手段を選ばないような価値観でした。「武士道」も本来はそうした精神を指す言葉として生まれたものです。しかし、近代になり、武士が消滅してから、「武士道」は、古い日本の道徳的価値を示す言葉として生まれ変わりました。そうした過程を、上代の神話から近代の新渡戸稲造までの諸書を通して追及しています。
私は、終章で書かれているような、戦争や軍事に関わる議論自体が否定される環境で育ってきましたので、戦争とは何か、そもそも哲学とは何か、ということに対してこれまであまりに無自覚に生きてきました。私自身も含めて、そんな人たちに向けて「戦争とは何か」といった、最も現代的かつ難しい問題に対して、判断材料と、ある一定の方向を示してくれたこの著作に敬意を払いたいと思います。なぜなら、世界を取り巻く今の情勢で、この問題に対して無自覚ではいられないからです。こんな著作を書かれた佐伯先生の今後の御研究も楽しみに見続けていきたいと思います。
『戦場の精神史―武士道という幻影―』
第三回〈角川財団学芸賞〉受賞について
博士前期課程 田村睦美
角川財団学芸賞は、日本の文芸・文化を扱った一般書を対象とした賞で、専門書を対象とする角川源義賞の姉妹賞として創設され、平成一五年から授与されています。対象となるのは、1、高レベルの研究水準にありながら、一般読書人にも読まれうる研究著作、2、卓抜な研究蓄積から生まれた、啓蒙的ないし評論的な著作、3、専門研究研究書からの敷衍応用として、一般性のあるテーマで独創的に構築された著作―評伝・都市や物事の個別史など、となっています。選考委員は黒田日出男堀切美山内昌之山折哲雄の諸氏です。
『戦場の精神史』は、日本の武士がだまし討ちなどせず、一騎打ちで正々堂々と戦ったというような見方は正しいのかどうかを疑い、戦場から生まれた倫理観の実像に迫ろうとした本です。実際には、合戦が繰り返された時代に育てられた倫理観は、勝つことを何よりも重視し、そのためには手段を選ばないような価値観でした。「武士道」も本来はそうした精神を指す言葉として生まれたものです。しかし、近代になり、武士が消滅してから、「武士道」は、古い日本の道徳的価値を示す言葉として生まれ変わりました。そうした過程を、上代の神話から近代の新渡戸稲造までの諸書を通して追及しています。
私は、終章で書かれているような、戦争や軍事に関わる議論自体が否定される環境で育ってきましたので、戦争とは何か、そもそも哲学とは何か、ということに対してこれまであまりに無自覚に生きてきました。私自身も含めて、そんな人たちに向けて「戦争とは何か」といった、最も現代的かつ難しい問題に対して、判断材料と、ある一定の方向を示してくれたこの著作に敬意を払いたいと思います。なぜなら、世界を取り巻く今の情勢で、この問題に対して無自覚ではいられないからです。こんな著作を書かれた佐伯先生の今後の御研究も楽しみに見続けていきたいと思います。
Copyright© 2005 Japanese Literature, College of Literature, Aoyama Gakuin University. All Rights Reserved.


