- 2019.07
- 川合康三『中国の恋のうた』(岩波書店)
山崎 藍(漢文学) - 2014.03
- 姫野カオルコ『昭和の犬』(幻冬舎)
川口則弘『直木賞物語』(バジリコ)
福山琢磨・植村鞆音 『直木三十五入門』(新風書房)
片山宏行(近代文学) - 2012.09
- 平野謙・小田切秀雄・山本謙吉 編集『現代日本文学論争史 上・中・下』
佐藤 泉(近代文学) - 2010.10
- 三上章『象は鼻が長い』
近藤泰弘(日本語学) - 2010.01
- 佐竹昭広『民話の思想』
佐伯真一(中世文学) - 2008.11
- 菊池寛『半自叙伝
/無名作家の日記』
片山 宏行(近代文学) - 2008.05
- 河上肇『自叙伝』
中野重治『歌のわかれ』
大上 正美(漢文学) - 2007.10
- 西郷信綱『古典の影』
高田 祐彦(平安文学)
川合康三『中国の恋のうた』(岩波書店)
山崎 藍(漢文学)
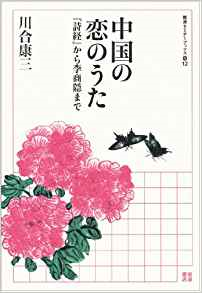
漢詩というと、どのようなイメージをお持ちでしょうか。
高校の漢文の教科書では、自然や戦争の悲惨さなどをうたう作品を取り上げることが多いようです。そのせいか、漢詩は堅い、わかりにくいと感じている方もいらっしゃるかもしれません。
ご紹介する川合康三『中国の恋のうた』(岩波書店)は、高校で扱われる機会があまりない「恋愛」がテーマです。
昔の中国では、儒家思想の影響もあって恋をうたう詩歌は少ないとされています。
しかし、人間が生活していれば恋愛は関心事のひとつ。中国も例外ではありませんでした。
例えば、中国最古の詩集『詩経』の「狡童」。
あのずるい人ったら、口もきいてくれない。
あなたのせいで、わたしはご飯ものどを通りやしない。
あのずるい人ったら、ご飯も一緒に食べてくれない。
あなたのせいで、私は息さえできやしない。
この作品を講義で紹介したところ、ある学生さんが「西野カナさんの『会いたくて会いたくて震える』みたいですね」と感想を書いてくれました。
確かに、恋人が離れていく不安を、「苦しい」「つらい」といった心情表現を用いずに、身体に変調をきたす様子をうたうことで表現している点は似ているかもしれません。
『詩経』は紀元前6世紀頃編まれたと言われています。
2500年以上前に生きた人も、現代と同じような感覚で恋愛を表現したのでしょうか。興味は尽きません。
他にも、激しい愛や断ち切れない恋など、様々なうたが、川合先生の美しい日本語訳とともに紐解かれます。教科書で触れる漢詩とは少し違った世界を垣間見ることが出来る、そんな一冊です。

