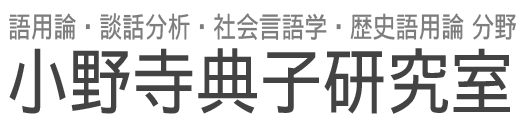研究活動

現在は、歴史語用論の「通時語用論」にあたるアメリカ英語の話しことばに見られる延長表現(general extenders; GEs)の機能の観察を進めている。GEsは米英語の発話末で文法化された表現と思われるが、表出機能が発達しており、コミュニケーション上有用な表現になっていると思われる(小野寺 2021.「間主観的から接続的への変化:意味機能変遷のもう一つの方向性」早瀬・天野編『構文と主観性』ほかをご参照ください)。
また、意味機能変遷(semantic change)研究で長年、核となってきた方向性「命題的>接続的>表出的」(Traugott 1982)の反例にも見える「間主観的>接続的」という方向性にも注目し、世界の言語で現象例が見られるようであり(IPrA2021でパネル発表)、考察を進めたい。研究書も計画されている。
最近の研究プロジェクトには次のものがある。
- 科学研究費助成事業 基盤研究(B)「日本語と近隣言語における文法化」
研究期間:2014年04月 ~2022年03月 PI: Heiko Narrog氏
研究分担者として参加。 - 青山学院大学総合研究所プロジェクト「英日語の「周辺部」とその機能に関する総合的対照研究」
研究期間:2014年04月 ~2016年03月 PIとして参加。
プロジェクトメンバー:澤田淳氏、Elizabeth Traugott氏、Joseph Dias氏、東泉裕子氏
成果本『発話のはじめと終わり:語用論的調節のなされる場所』(小野寺編 2017. ひつじ書房)
また、2019年度、構文研究会や動的語用論研究会にも参加。隔年開催のIPrAでパネル発表、日本語用論学会大会などに参加しています。


以上