エ ッ セ イ
桜 の 季 節 日置 俊次
桜の季節になりました。
新入生の皆さんは、大学のキャンパスに舞う桜の花に出会い、入学の喜びもひとしおであることと思います。
桜には、しかし人々の喜びの記憶だけが結晶しているわけではありません。
歌人の馬場あき子は、戦時中に「無惨に若く美しく散ることのみが讃えられて」多くの若者が死に急ぐ姿を見てきたため、長く、桜を歌うことができなかったといいます。
さくら花幾春かけて老いゆかん身に水流の音ひびくなり 馬場あき子
数百年もの樹齢を重ねていく桜の樹木が湛える悠久の時間と、限りある人間の生。
両者が生命の音、すなわち水の音を通して響きあうさまが、この短歌から伝わってきます。
そういえば馬場あき子の結社に所属する若い歌人、川野里子は、桜と母親の姿とを次のように描いています。
母は、まるであの世のように日常を白く染めてゆく桜を怖れている。自分の周りが真っ白く染まってしまわぬよう、家族が暮らした家が桜に占領されてしまわぬよう。桜の美しさに攫われてしまわぬよう、花びらを掃き続ける。 (「桜の祝祭、桜の暴力」朝日新聞04/3/27夕刊)
こうして桜の美しさへの恐れを描く彼女はこんな歌を詠んでいます。
哀しみと愛しみはひとつ遠く夜の古木ま白き桜花を噴きぬ 川野里子
「愛しみ」は「かなしみ」と読みます。
出会いと別れ、喜びと哀しみの交錯する窓として桜を見つめましょう。
その窓から、豊かな文学の宇宙が拓かれていくはずなのです。
0
高校生のみなさんへ
日本文学科
ホームページ
1
4
2
青山通り
青山と相模原
短歌ゼミ

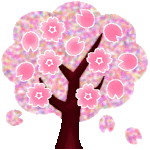
桜 の 記 憶 〜 時 代 を つ ら ぬ く 魂 〜
「古事記」に登場する女神、木之花咲耶姫(このはなさくやひめ)は富士山頂から種をまいて花を咲かせたといわれます。
「桜」の語源にはさまざまな学説がありますが、一説にこの「さくや」が転化したといいます。
そんな桜の美しさには「散る」という魅力が含まれていて、それが人の心を撹乱し、狂わせることも、万葉集の頃から歌に詠まれています。
あしひきの山桜花日並べてかく咲きたらばいたく恋ひめやも 山部赤人
もしも山の桜が散らないで長く咲いていてくれるのであれば、それほど恋しさも募らないのかもしれない……。
赤人の歌は、そのまま現代のわれわれにも受け入れることができるでしょう。
桜花散りぬる風のなごりには水なき空に波ぞ立ちける 紀貫之
桜が舞い散っている空に風が流れていきます。その風のなごりをみつめると、水に満たされているはずもない空に、まるで波が立っているようです……。
現代でもそのまま理解できる光景ですね。
桜の季節になるといつも花と戯れ、散るのを繰り返し惜しんだ西行は、およそ二百三十首もの桜の歌を残しています。
ねがはくは花の下にて春死なんその如月の望月のころ 西行
如月(2月)、望月(15日)と願ったとおり、西行は2月16日(新暦では3月)に亡くなりました。その桜好きは徹底しています。
近代でも、もちろん桜は多くの歌人たちに愛されています。
清水へ祇園をよぎる桜月夜こよひ逢ふ人みなうつくしき 与謝野晶子
満開の桜に誘われた人々が歩く夜。京都の夜桜の不思議な、どこか妖しいまでの美しさに照らされながら、人々はなんとも知れない心騒ぎを覚えているのでしょう。
万葉集のころから、歌は時代をつらぬく人間の深い魂をみつめ、その魂を湛えつづけています。
桜 に つ い て の 読 書 案 内
上に記した桜のお話は極めて断片的なものに過ぎません。
短歌以外の分野も含めて、ほんのすこしだけですが参考図書をあげておきましょう。
辻 邦生 『西行花伝』
(新潮文庫)
西行の生涯を描く長編歴史小説。高橋英夫『西行』(岩波新書)、吉本隆明『西行論』(講談社文芸文庫)もおすすめ。いずれも桜についての本ではありませんが……。辻邦夫の小説の一節を引用します。
そのとき、胸の奥底から、突然、「この世がたまらなく愛しい」という叫びが、悲鳴のように迸り出てきた。私の魂は物怪に憑かれたようにこの世の中に走り出ていた。私はもうそこに立っていることができなかった。桜の花の前に膝をつき、片手で上半身を支えながら、私は、白い光の泡立つ激流に洗われていた。
梶井 基次郎『檸檬』 (新潮文庫ほか)
おすすめの文庫本です。所収の短編「桜の樹の下には」をご紹介します。書き出しを引用しましょう。
桜の樹の下には屍体が埋まっている!
これは信じていいことなんだよ。何故って、桜の花があんなにも見事に咲くなんて信じられないことじゃないか。俺はあの美しさが信じられないので、この二三日不安だった。しかしいま、やっとわかるときが来た。桜の樹の下には屍体が埋まっている。これは信じていいことだ。
佐藤俊樹『桜が創った「日本」――ソメイヨシノ 起源への旅――』(岩波新書)
新刊です。やや大づかみな文章ですが、「人工物」としてのソメイヨシノと日本人との関係を論じています。
経済的な面からいっても、ソメイヨシノは繁殖させやすい。接木の成功率が高く、成長も早い。だから、大量生産にも向いているし、需要がふえたりへったりするのにもあわせやすい。近代社会においては桜も市場経済の一商品である。生産者からすれば、ソメイヨシノはとても経済的な品種だった。
坂口安吾『桜の森の満開の下』(講談社文芸文庫、ほか)
桜の恐ろしさと人間の恐ろしさとが重なり、まがまがしい因業のように、しかし不思議に明るく描かれています。安吾の毒を味わってみましょう。書き出しを引用します。
桜の花が咲くと人々は酒をぶら下げたり団子をたべて花の下を歩いて絶景だの春ランマンだのと浮かれて陽気になりますが、これは嘘です。なぜ嘘かと申しますと、桜の花の下へ人がより集まって酔っ払ってゲロを吐いて喧嘩して、これは江戸時代からの話で、大昔は桜の花の下は怪しいと思っても、絶景などとは誰も思いませんでした。
谷崎潤一郎『刺青』(新潮文庫、ほか)
芥川賞受賞の金原ひとみ「蛇にピアス」の原型ともいえる短編。明治43年発表ですが、いささかも古びていません。
画面の中央に、若い女が桜の幹へ身を寄せて、足下に累々と斃れて居る多くの男たちの屍骸を見つめて居る。女の身辺を舞いつつ凱歌をうたう小鳥の群、女の瞳に溢れたる抑え難き誇りと歓びの色。それは戦いの跡の景色か、花園の春の景色か。
青山学院大学文学部日本文学科
更新ページ

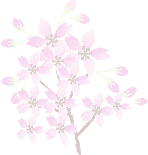

青山キャンパス(3月25日、日置撮影)


ハクレン (3月25日)
青山キャンパスの椿
(3月25日)



卒業式の日の正門付近 (3月26日)



(更新 2005年7月10日)









病院跡と茂吉の墓
歴史を刻む外国人墓地

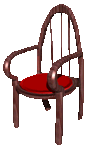
★更新★ 2006年2月21日 ![]()
早いもので、ホームページを開設して1年がたちました。
カウンターが4000を超えました。
訪れてくださった皆さんに感謝します。
春の気配がただよい、キャンパスの入学試験合格者発表の掲示板に、受験生やその父兄が集まり、ケータイで記念写真を撮ったりしています。
合格された受験生の皆さん、本当におめでとうございます。
しかし、今は2月。
まだまだ寒い日が続いています。
この冬、キャンパスはしばしば雪で真っ白におおわれました。
まだ春の雪が、一度は降りそうですね。
本当の春はまだまだ先のようです。
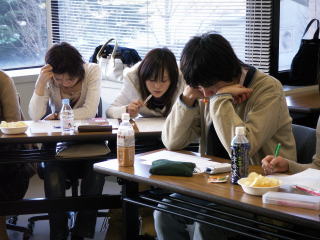



(青山キャンパスでいつも最初に咲く桜)
2006年3月24日撮影










