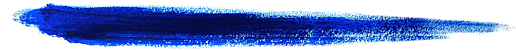ゼミの方針
皆さんは、これまでに多分どこかで、「われ思う、故にわれあり」という言葉を聞いたことがあるでしょう。これは17世紀前半のフランスの哲学者、ルネ・デカルト(René Descartes)の言葉です。そして私のゼミでは、今のところ、そのデカルトに取り組んでいます。哲学のゼミだという点では、フランス文学科の多数のゼミのなかでも、やや異色だと言うことができるかもしれません。先の言葉は、デカルトの哲学のなかでも最も原理的な事柄を扱う「形而上学」のなかの有名な言葉ですが、その他にもデカルトは様々な仕事を残しました。数学上の仕事は、それ以来、21世紀初頭の今に至るまでとぎれなく続くこの学問の隆盛を可能にした礎[いしずえ]を置くものでしたし、物理学、天文学、生理学なども体系的に作り直しました。そればかりではありません。およそ人は生きている限り、行為せずにはいられないものです。「何もしない」ということですらが、何もしないことに「する」という選択をすることにならざるをえないのですから。そのように人が生きて行為するに当たって、いったい何を指針として臨めばよいのかという道徳の問題についても、また行為しつつ生きている限り、人の心を様々に彩らずにはいない「喜び」や「悲しみ」、「怒り」や「感謝」、「愛」や「憎しみ」などの情念の本質と意義についても、傾聴に値する見事な文章を書き記しています。
「つるべをおろせば、必ず黄金と善意がいっぱいに汲み出せる無尽蔵の泉」デカルトから二世紀半のちの哲学者ニーチェのこの言葉は、そのままデカルトのテクストについてもあてはまります。みなさんも一緒にこの泉につるべをおろしてみませんか。どんな善意とどんな黄金が汲み出せるかを楽しみにしながら。
みなさんの参考になることを願って、私自身が汲み出したものを二つだけ掲げておきます。いずれの内容もデカルトの最初の著作、『方法叙説』に関わるものですが、特に最初の文章では読者像として若い人々を想定しています。第二の文章にはそのような限定はありませんが、やはり一般読者向けに作成した文章です。
デカルトの青春
青春は麗し
されどあわれはかなし
今を楽しみてあれ
何事も明日ありとは
定かならねば
メディチ家のロレンツォによるこの詩は、いかにも毀たれ易そうな「今」をひたむきに享受しようとする初々しさが痛々しいまでの印象を残す、典型的な青春の唄の一つである。デカルトにも青春はある。しかしそれはこの唄の表現するものとはよほど異なっていた。デカルトを動かすものはもっとはるかに質実な力、深く自己に徹して自己を支配しつつ生の道の全体を歩み通そうとする形成力、卓越した知的な鋭敏さを備えて成熟をめざす形成力である。デカルトも詩は好んだ。しかしそのデカルトが青春のある折りに、自己のありようを銘記しておくための里程標として選んだのは、四世紀のラテン詩人アウソニウスの詩句である
いかなる生の道にか
われ従わん。
「今」とはいとおしまれるべき「今」なのではない。行方のしれぬ明日という時の奈落にかかった、そこだけが輝かしい虹なのでもない。デカルトにとっての「今」とは歩み通されるべき生の一契機にすぎない。「不安」や「恐れ」がないのではない。だが今日の輝きを葬る明日の転変を恐れる恐れではない。不安の淵源は明日よりもむしろ今、現在にある。見通しがたい「生の道」を見定めて歩み通そうとするにあたって、「今」がいつもある「分かれ道」の景色を呈して「決断」を迫ってくるからである。決断は「今」下さなければならない。私が私の心ないし精神を働かせる時間は必然的に現在であるからだ。何もしないことですらが否応なしに何もしないことに「する」選択をすることになる。自分がこうした危地に、今、晒されているということ、これが不安の正体である。そのただなかをたじろがずに歩みぬくことなしには、いかなる生の道も開けてこない。ここには叙情へと傾斜する心よりも見通そうとする知性の働きと危地に臨む意志の姿勢がある。
『方法叙説』の前半は、デカルトが一人称で自分の青春を語った自伝である。だが「青春の記録」という言葉が予想させるような、初恋の思い出やほのかな性の目覚めなどが記されているわけではない。デカルトの情熱を語るのは例えば次の文である。
「自分の行為において明晰に見、確信をもってこの生を歩むために、真を偽から区別する術(すべ)を学び取りたい、私は常々そう熱望していた。」
デカルトは「真を偽から区別する術」、つまり「方法」を自ら見つけ出して定式化することになる。その小手調べのようにして、数学の歴史を変えた革命的な発見が報告されもする。だが達成された成果の側から『叙説』を読むだけでは、『叙説』の自伝的なスタイルに密着することはできない。デカルトを始めから動かしてやまないものがここにはあらわれている。砂漠で水を求めに求めて蜃気楼に欺かれる者が、乾き、つまり水の欠除に苦しんでいるように、何かが欲しいと熱望する者は、手に入れたい当のものを自分が欠くという貧しさのただなかを生きている。『叙説』一部が控えめに語るように、デカルトは当時の最高の教育を受けた。単にひとかどの者として社会に身を立てることが望みならば既に十分な出発点だっただろう。だがデカルトには教育が授けた既成の知のうちに、基礎が不確実なままに無益に繁茂する教養、つまり「生に有用な事柄についての明晰で確実な知識」の欠除しか見えなかった。自分の心が真実には何を大切にし、何によって動かされているかということのおぼろげな自覚、自分自身との最初の出会いである。
人間の魂の容量と精神の豊かさは、精神がどのような貧しさと乾きを生きるかによって測られることがある。デカルトはこの乾きに徹底して向き合う道を選んだ。踏み固められた既成の教養、「書物による学問」という二次的な夾雑物をまとめて放棄して、一人で道なき道にのり出そう、世間のなかで自己を鍛えてじかに「世界という大きな書物」に取り組もうとしたからである。この構えを背景においてはじめて、先の文はデカルトの青春の衝迫を語るものとなる。『方法叙説』を読む若い読者はデカルトの筆使いに欺かれるかもしれない。四十路に入った壮年の男性の重たげに熟した文章だからである。だがその奥に綴り込まれているのは思いの外に激しい青春の原姿である。自分の手で掴み取った方法による知的な鍛錬を積み重ねて、デカルトが真理の探究を生涯の仕事として改めて選び直し、そこから日々得られる純粋で満ち足りた喜びについて語るとき、それはこの精神の独歩行が遂に乾きを満たす泉を探り当てたことを意味している。感情に関する事柄は排除されているのではないが主題ではない。『叙説』はあくまでも精神と知性の自伝、精神を動かすある大きな願いが自己を充足するまでの軌跡を語った極めて独特な自伝なのである。
『叙説』も半ばをすぎると新たな色彩を加えてくる。生(き)のままの自己の生涯よりも、取り組んだ真理の探究の成果を語るほうに比重が移るからである。そのデカルトの仕事のなかで、「自己について語ること」にはまだ何らかの役割があるだろうか。まず『叙説』四部の形而上学ではどうか。確実な知の探求はここで最も鋭い様相をみせる。若きデカルトが既成の教養を放棄したことは見た。だが誰にせよ、書物で学んだ表層の教養が廃棄できたとしても、なお残るのは不確かな日常の生である。この日常の生こそを見直すこと。世界や私自身についての様々な思いなし、私のうちに根を張っているあらゆる信念を順を追って疑いに付し、たとえそれらの信念のどれ一つとして真ではないとしても、そのように疑う私自身の存在は疑いえないことに突き当たって「我思う、故に我在り」を原理にたてる。続けて、その私自身も含めて、あると言える限りのあるもの一切を現にあらしめている神の存在が証明される。こうして根拠についての把握を知的に浄化した上で、改めて日常の生に復帰するのである。デカルトといえば誰でも思い浮かべる「我思う、故に我在り」という原理が、既に一人称でなければ表現できない。だが注意すべきはこの一人称がそれまでの『叙説』を支えてきた「自伝的な」私とは異なる普遍的な射程をもっているということだ。デカルトの形而上学の最も緻密な表現たる『省察』でも、一人称的な思索のスタイルのこの質は変わらない。『叙説』四部や『省察』の読者は、テクストに記された「私」という文字が探求の道筋を真剣に辿り直す自分自身の私を指すことをまざまざと経験させられるだろう。決して自伝を語る「私」のように、過去に実在したある語り手を指して終わるのではない。だからこそ「我思う、故に我在り」が誰にでも妥当する原理としての資格をもつのである。
「我在り」の確定はデカルトが打ち込んだ自然学(物理学)の研究とどのように連動するのか。この時代の宇宙観の大転換に注目しよう。天動説から地動説への転換である。被造物の冠たる人間の住む大地を中心に置いた世界観を脱中心化することは宗教的にも習俗的にも受け入れ難いことだった。人類は無限の空間のなかの流浪の民と化するのではないか。だが真の問題はまだその先にある。それを思弁的な仕方で一挙に引き出してみせたのは、たとえばジョルダーノ・ブルーノだった。空間が無終的に拡がっているとすれば、その中には太陽系のような世界システムもまた無際限にあるだろう。世界の中心が地球から太陽に変換されるだけではない。この宇宙にはそもそも中心などはない。この説を伝え聞いたケプラーの言葉が遺されている。「それは不気味である」と。ケプラーには何が見えたのだろうか。自らの惑星運動の研究が切り開きつつある新たな地平の奥に隠れているもの、もはや親しく語りかけてくることのない無限の空間のなかに投げ出されて定点なくさまよう人間の新しい定めをかいま見て慄然としたのだろうか。そしてこの言葉のなかに後のパスカルの『パンセ』の響きが聞こえないだろうか、『この無限の空間の永遠の沈黙は私を畏怖せしめる』と。デカルトはこのようにはたじろがなかった。どこにも中心がないということはどこが中心であってもよいということだ。私自身がこの無限の蒼穹のなかに飲み込まれて消失するかのごとくに恐れる必用はない。「我在り」は拠り所となる第一の原理だからである。この宇宙がその果てしなさのままに「ある」ならば、あるもの一切をすべてあらしめている神の秩序は現にその隈々にまで及んでいるのでなければならない。この世界という書物の全体が、同じ神によってあらしめられているわたしの遂行する知的な探求に委ねられている。自分の発見を自分が真に自分のものとすることがどれほど困難なことか。この時代の知的な英雄はデカルトだったのである。
『方法叙説』から
デカルトを読むようになったそのそもそもの始まりから、様々な疑問を潜在させて心に掛かったまま、容易に消え去ろうとしない一節がある。それは他でもない『方法叙説』第一部の記述が、『良識はこの世で最も公平に分配されているものである』と書き始められるあの有名な一種の前置きを終えて、この書物の本来の面目たるデカルトその人の知的な自伝の語りに転じようとするその冒頭に置かれた一節である。『私は子供の頃から文字による学問のなかで育てられ、この手だてで人生に有用な全てのことについて明晰で確実な知識が得られると説き聞かされていたので、それを学び取ろうとするこの上もなく強い望みを持っていた。』無論のことこれに続く文章は、直ちにこの人文学(『文字による学問』)への失望を語りはする。その意味ではこの一節も、デカルトの生涯の知的な幕開けの、ある一挿話を述べたに過ぎないと読むこともできよう。そしてそれは、事が単に「人文学」に関わる限りでは、事実その通りなのだ。だが人文学そのものを除いてもまだ残る二つのもののあいだの相関関係-『学び取ろうとするこの上もなく強い望み』と、この望みにおいて欲せられ・志向されている『人生に有用な全てのことについて明晰で確実な知識』とのあいだの相関関係-はどうだろう。これも人文学の挿話とともに過ぎ去るべきものだっただろうか。それともこの相関関係は、全挿話が言わばその廻りに展開する機軸として常に変わらず生きられ維持されたまま、まさしく欲せられている当のそのものが人文学において満たされる望みを失ったということなのか。そして一人称で過去を物語るという、デカルトが『方法叙説』で採った歴史記述のスタイルが、己の生涯ではほんの前景の挿話として過ぎ去った人文学に、この望みを暫定的に仮託してみせたにすぎないのか。少なくとも私にはこの「望み」の語が既に、なかなかにその実質の捉え難いものである。
ある論者は、この節全体のうちに後年のデカルトの虚構をしか認めない。わずか八歳の子供が、既に人生に適用可能な、そして確実な学の理念によって動かされているなどとは、と。また別の論者がここに読むのは、デカルトを教育したジェズイットの先生達の受け売りである。歴史形成力を失った後期スコラの煩瑣哲学に対して、ルネッサンスの人文学の「有用性」は、当時は全くありふれたテーマであった、そしてジェズイットの教育理念の進歩性はまさしく人文学の成果を積極的に取り入れたところにあったのだ、と。勿論この一節のなかに、執筆当時のデカルトの現在が入っていないということはあり得ない。四十路に入った一人の人間が改めて自分の過去に向き直り、その意味を我とひととに了解させようと語り出すその時に、一種の解釈学的循環が働くのは当然のことである。また一切を人文学のプロパガンダに帰するのも芸のない話しだ。事実、失望を経て自らの学んだ学院を、言い換えれば文字と書物と教師による学問を捨て、一人『世界という大きな書物』のなかで学ぶ途を行こうとするデカルトは、わざわざ同じ表現を用いて次のように記している。『そして私は自分の行為において明晰に見、確信をもってこの人生を歩むために、真を偽から見分ける術を学び取りたいというこの上もなく強い望みを相変わらず持っていた。』極度に言葉を惜しむデカルトにして、この繰返しは決して卒爾のものではあり得ない。つまり『この上なく強い望み』そのものは、直ぐに見切りをつけた人文学の有用性の思想を超えて、なお維持されているということだ。
『この上なく強い望み(extrême désir)』とは文字通り最上級の過激な表現で、デカルトも学んだと思われるアリストテレス系の道徳哲学の、「中間(中庸)」を尊ぶ精神とは必ずしも折り合いがよくはない。しかもしばらく後に世に出るラテン語版の『方法叙説』では、この箇所の表現は更に強められている。『私は学び取りたいという信じられない程の望みに燃えていた。』そしてこの系列に属する表現を追跡して行くと、やがて『哲学原理序文』のなかの次のような文章に出会う。『感覚の対象に惹かれきったままになっているために、時にはそれから身を離して、それとは別の何かしらより大きな善を望むということをしないほど、それほど高貴さに欠ける魂は存在しない、たとえそのより大きな善が何に存するかをしばしば魂は知らないとしても。』
より大きな善を欲するが故にこそ、却ってその志向されているものがここにないという激しい欠乏を生きる現在の知覚。こうして読んでくれば、ここで半ばプラトン的なエロースに比定して語られているものが、そして『方法叙説』で人文学の孕む夢に投影して語られていたものが、まさしく真正の知への渇きとしての「哲学の始まり」のイデーに他ならないことがわかる。およそギリシャの昔から、プラトン風の求心的な哲学の営みとイソクラテス風の人文学的教養との間には、常に変わらぬ複雑な葛藤があった。
では、この「望み」において欲せられているものを限定する、『人生に有用な全てのこと』の句の方はどうだろうか。デカルトとデカルト主義とからは現に様々なものが流れ出て、しかもそれらの多くが現在の複雑なデカルト批判の諸潮流へと逆流して行くので、この句もまた私には読み解くに難いものである。例えば、有用性すなわちある種の利害(intérêt)の観点から算定された功利性。ここでは確実性の探求は利得を離れた真に自由人的な高貴な営みというよりも、そもそもの始めからある種の知の功利性という偏向を帯びている。デカルト自身が推進した知による自然の有効な支配(「自然学」の構成)という理念と、そこから生じて現に生活を快適ならしめている様々な技術的諸成果。そしてそれらの成果が却って現在では、我々の現実を圧迫し精神的視野を狭めているという評価、等々。こうして近代批判のポレミックの核には、殆ど常に何らかの形のデカルト批判がある… 私自身は、今この種のポレミックの場に参加しようとは思わない。ただ「有用性」の思想そのものを、特殊デカルト的な、そして特殊近代的な偏向としてしまいかねない考え方だけには、一応疑問を附しておきたいと思う。何らかのより大きな善が模索されつつ掴まれてくるということ、それは私たちがその「よきもの」を欲し必要として本質的な関心(intérêt)を寄せ、心あるいは魂をそのものの方へと向け直すことである。他の様々なものは、私たちがこの「よきもの」において欲し意欲している事柄の見通しの中に引き入れられる。私たちの魂が本質的に何の方を向いているかということと、何らかの大きな善が与える全体的な視座ないし視野への適合性の連関を離れて、いかなるものの有用性を語る余地もありはしないのである。
例えば、所謂「近代」を遡った「中世」の代表的な作物、トマス・アキナスの『神学大全』の知的構成も、やはり「有用性」への考慮によって全体が統括されている。この書の構成を決する要の箇所で、そもそも知の問題に関わるのに哲学的諸学以外に何らかの教えが必要であるかどうかという問を立てたトマスは、大略次のように答えているからだ。聖書は人を教え、戒め、矯正し、義に導くことに向けられているが、この教えは人間的理性の埒外にある神の霊感によるものである。したがって哲学的諸学のほかに神感による知を持つことは有用である、と。そしてこの配慮が、この書における聖書と哲学的探求との協同関係、また啓示神学と自然神学との協同関係を導いていく。「有用性」とは優れて体系的な概念なのである。
トマスに昏い私には断定がはばかられるが、『人生に有用な全てのこと(tout ce qui est utile à la vie)』という『方法叙説』の表現方式は、その「有用性」の思想とその「有用性」が他ならぬ「人生」にとっての有用性であるという点を含めて、そのままトマスによっても受け入れられるものであったろう。違いはむしろその手前にあるもの、「人生(la vie)」、生、今ここにおける私たち自身の在り方-その中で私たちが何に心を向けているかを含めて-への理解そのものにある。
「聖なる教え」における問題はこの生を生きる個々の魂の救済の確保である。個々の魂はすべて自らの救済へと心を向けているし、また向けていなければならない。すべては啓示に基づく救済の確保と促進という目的へ向けて算定され、予めこの連関への適合性のなかで知るに値するものが決定されているのである。知ることに対して相関的に与えられた人生に有用な事柄のすべては、ここではこの様な見通しに支配されている。
デカルトではそうではない。学院で学んだ事柄に対してデカルトが与える総括的評価の中で最も印象的なのは、自らが関わろうとする知の領域からの、『天国を勝ち得る』ものとしての『神学』の切り離しではないだろうか。啓示の問題が消えたのではない。「生」を画する限界としての死を思うことが止んだわけでもない。自らの知的投企の炎が及ぶ領域のその外で、デカルト個人は啓示の宗教に身を委ねていただろう。トマス以降の唯名論の成立による信仰の問題と知の問題の改めての分離、この唯名論の系譜からの宗教改革の成立、そしてヨーロッパに荒れ狂った宗教戦争の嵐、トマスとデカルトの間には様々なことがあった。
知ろうとする『この上もなく強い望み』が己の地歩を確保すればする程、その強烈な光の当る部分に対して常にますます奥深く引きこもる深部から、同じ十七世紀にあげられた声に次のような言葉がある。『無用にして不確実なデカルト』、と。デカルトの意味における「有用性」を否定したパスカルには、同時にこれがデカルトの意味における「知ろうとする欲求(libido sciendi)」の否定になることがわかっていたはずだ。この魂の向き直しを引き起こすために、デカルトとは別して本質的によりレトリシャンであるパスカルが、一体どれ程の努力を傾注し尽くしたことか…
『方法叙説』の短い一節を通して、先立つ時代と同時代とやがて来る時代の、様々な潮流が谺し合うのが聞こえる。無論、若きデカルトその人は、言わば本能的に己の内的な促しに従って、自らの途を行こうとしているだけである。己の途を行く者の、星座のような孤独と言うべきだろうか。
« 教員ゼミ紹介へ戻る